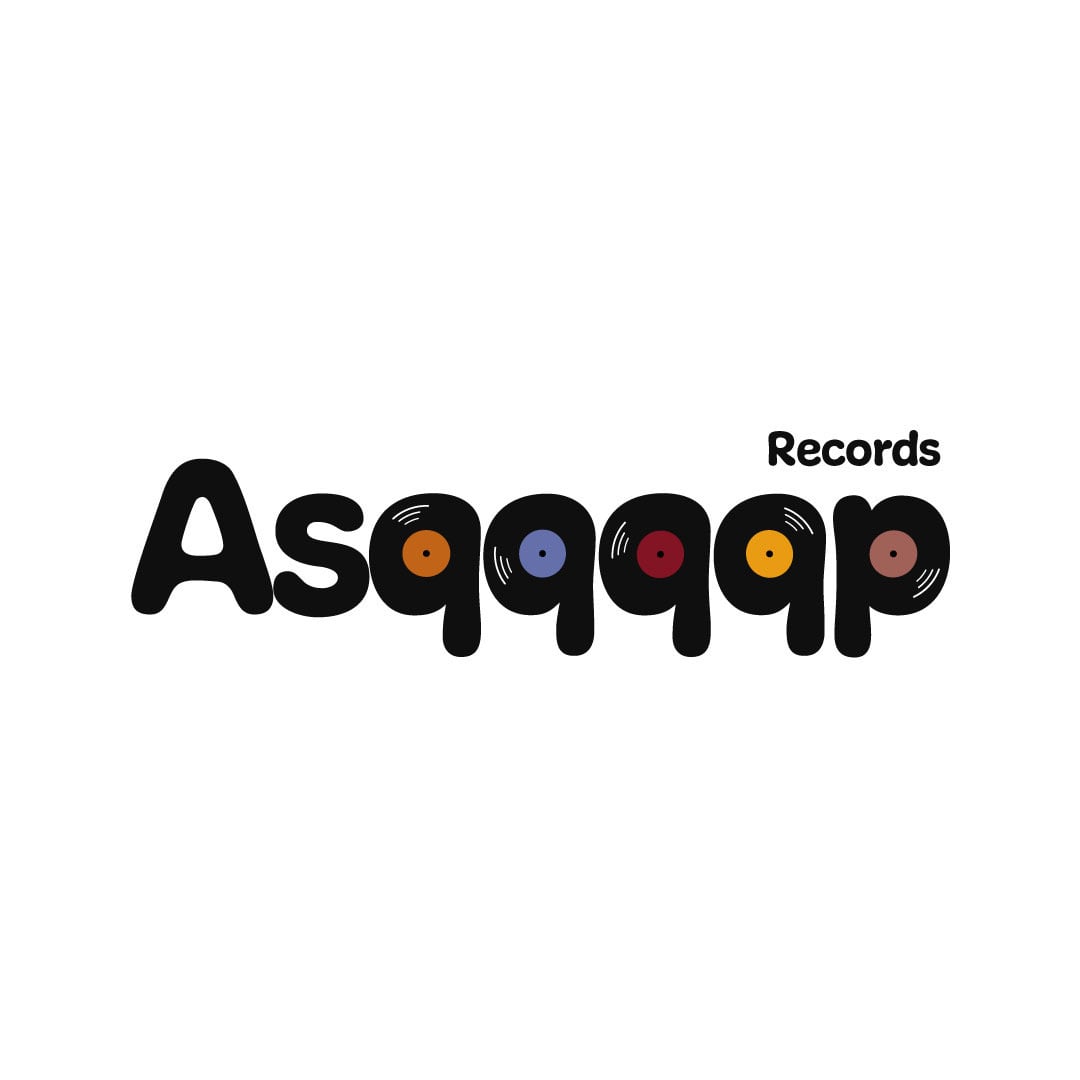-

Eric B. & Rakim – I Know You Got Soul (Six Minutes Of Soul / The Double Trouble Remix)
¥2,000
基本情報 Label:Cooltempo – COOLXR 146 Format:Vinyl, 12”, 45 RPM Country:UK Released:1988 Genre:Hip Hop Style:Golden Era, East Coast, Remix Condition:盤質 VG+ / スリーブ VG+ ⸻ トラックリスト A1. I Know You Got Soul (The Double Trouble Remix) B1. I Know You Got Soul (LP Version) B2. I Know You Got Soul (Acappella) ⸻ サンプリングネタ ・Bobby Byrd “I Know You Got Soul” ・James Brown “Hot Pants (Bonus Beats)” このブレイクビートの再構築が、後のリミックス文化とクラブシーンを牽引。 ⸻ 小ネタ・エピソード オリジナルは1987年『Paid in Full』収録のクラシック。 このUKプレスはDouble Troubleによるリミックス盤で、クラブ仕様のアレンジが光る人気12インチ。 Rakimの静かなフロウと、Bobby Byrd由来のソウルフルなグルーヴが融合。 Public EnemyやEPMDにも影響を与えた“サンプリングの教科書”的トラック。 Cooltempoレーベルは当時のUKクラブカルチャーの中でも特に信頼の厚いレーベルで、 この盤はその象徴とも言える存在。 ⸻ Condition 盤面 VG+(軽微なスレあり、再生良好) スリーブ VG+(軽い角スレ) ⸻ ASqqqqpからの一言 ヒップホップのソウルを形にした一枚。 Rakimのラップはまるで“音の上を歩く詩”のようで、 ビートはクラシックソウルと黄金期の衝突点。 針を落とした瞬間、時代が戻る。 ⸻ Eric B. & Rakim / Golden Era / Double Trouble Remix / Cooltempo / Bobby Byrd Sample / Paid In Full
-

Doctor Funnkenstein & DJ Cash Money – Scratchin’ To The Funk【12″ US盤 / 1985年 / Pop Art Records】
¥3,000
オールドスクール・ヒップホップの歴史を語る上で欠かせない一枚。 Doctor FunnkensteinとDJ Cash Moneyによる12分超のスクラッチ・ミックス「Scratchin’ To The Funk」を収録したUS盤12インチ。 ベースにはTrouble Funk「Pump Me Up」を引用し、スクラッチを駆使して再構築。後にPublic Enemy – “Fight The Power” の冒頭でも使われるなど、ヒップホップ史に確実に刻まれた重要作です。 片面12分のPart I & Part II構成は、当時の現場感と実験精神をそのまま閉じ込めた仕様。ファンクからヒップホップへ橋渡しされた“グルーヴの遺伝子”を体感できる一枚です。 レーベル / フォーマット • Label:Pop Art Records • Format:12″ Vinyl, 33⅓ RPM • Released:1985年 • Country:US Condition Vinyl:VG+ Sleeve:VG Asqqqqpの一言 この盤を聴くと、ヒップホップがまだ“クラブの実験”だった時代の熱がそのまま蘇る。後のサンプリングやDJカルチャーに大きな影響を与えた一枚として、持っておきたいクラシックです。
-

Eric B. & Rakim – As The Rhyme Goes On
¥1,000
「As The Rhyme Goes On」は、Rakimの詩的なリリックとEric B.の洗練されたプロダクションが融合した楽曲で、ゴールデンエイジ・ヒップホップの象徴的な作品です。この楽曲は、彼らのキャリアにおいても、ヒップホップ全体においても特別な位置を占めています!!!!! 背景と制作秘話 「As The Rhyme Goes On」は、Eric B. & Rakimのデビューアルバム『Paid in Full』(1987年)に収録された楽曲で、1988年にシングルカットされました。この楽曲はRakimの洗練されたリリックとEric B.のミニマルなプロダクションが特徴で、1980年代後半のヒップホップの方向性を決定づけた一曲です。 • 革新的なリリック: Rakimは、「フロウ」の概念を進化させたMCとして知られています。この曲では、彼のスムーズで高度なリリックテクニックが際立っています。 • プロダクション: Eric B.のシンプルながら重厚なビートは、サンプリングを中心に構築され、リスナーの集中をRakimのリリックに引き寄せます。 歌詞の特徴とメッセージ 歌詞は、RakimがMCとしての自信とスキルを強調した内容になっています。彼の哲学的な視点とポエティックな表現が融合したリリックは、当時のヒップホップとは一線を画すものでした。 • 象徴的なリリック: “As the rhyme goes on, I’m a phenomenon…” 自身を「現象」と表現することで、MCとしての影響力と創造性を誇示しています。 • リリックのスタイル: テクニカルで言葉遊びに富んだスタイルが特徴的。彼の冷静かつ落ち着いたデリバリーは、他のMCとの差別化に成功しています。 音楽的影響と評価 「As The Rhyme Goes On」は、Eric B. & Rakimがヒップホップに与えた革新の一例として挙げられます。 • プロダクションの革新: Eric B.は、サンプリングを駆使したプロダクションで知られています。この楽曲も、ファンクやソウルのループを活用し、クラシックなビートを作り上げています。 • 批評家の評価: この曲を含む『Paid in Full』は、ゴールデンエイジ・ヒップホップの代表作とされ、現在も多くのリストで「史上最高のヒップホップアルバム」に選ばれています。 サンプリング情報とトラック構成 「As The Rhyme Goes On」は、Eric B. & Rakimらしいシンプルかつ効果的なサンプリングが特徴です。 • サンプリング元の楽曲: • 正確な元ネタ情報は明示されていませんが、彼らのプロダクションはファンク、ソウル、ジャズからインスピレーションを得ていることで知られています。 • リミックス: シングル盤にはChad Jayによる「Pumpin’ The Turbo - Chad Jay In Effect」バージョンが収録され、原曲とは異なるエネルギーを持っています。 BPMとDJカルチャーへの影響 • BPM: 約100 BPMのミッドテンポは、クラブでのプレイや他の楽曲とのミックスに適しています。 • クラブでの使用: 「Pumpin’ The Turbo」バージョンは、エネルギーを高めるリミックスとしてDJに人気があります。 JP-Reissue-シュリンク Media Condition Very Good Plus (VG+) Sleeve Condition Very Good Plus (VG+) Label: 4th & Broadway – 12 BRW 106, 4th & Broadway – MR-065, Island Records – 12 BRW 106, Island Records MR-065 Format: Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Reissue Country: Japan Tracklist A As The Rhyme Goes On (Pumpin' The Turbo - Chad Jay In Effect) 6:10 B1 As The Rhyme Goes On (Elpee Version) 4:00 B2 Chinese Arithmetic 4:07 Credits Photography By [Back] – Anna Arnone Photography By [Front] – Adrian Boot Producer – Eric B. & Rakim
-

Melle Mel – The Mega-Melle Mix
¥700
このレコードは、1985年にSugar Hill Recordsからリリースされた12インチシングルで、Melle Melの代表曲をメドレー形式でまとめた「The Mega-Melle Mix」と、B面には「Pump Me Up」が収録されています。「The Mega-Melle Mix」は、DJ Sanny Xが手掛けたリミックスで、Melle Melのエネルギッシュなパフォーマンスが詰まった一枚となっています。 【サンプリングネタ】 ▫️ The Mega-Melle Mix このメドレーは、Melle Melのヒット曲「Step Off」「The Message」「Beat Street」などを組み合わせたリミックスで、各楽曲の要素を巧みに融合させています。オリジナル曲自体が他の楽曲をサンプリングしている場合もありますが、このリミックス自体は新たなサンプリングを使用せず、既存のトラックを再構築しています。 【その他】 「The Mega-Melle Mix」は、1994年にリリースされたコンピレーションアルバム『Message from Beat Street: The Best of Grandmaster Flash, Melle Mel & the Furious Five』にも「Step Off Megamix」として収録されています。このアルバムでは、Melle Melの代表的な楽曲がまとめられており、彼の音楽キャリアを振り返ることができます。 また、Melle MelはGrandmaster Flash and the Furious Fiveの主要メンバーとして知られ、ヒップホップの黎明期から活躍してきました。彼の力強いラップと社会的メッセージを込めたリリックは、多くのアーティストに影響を与えています。 「The Mega-Melle Mix」は、彼の音楽的才能と革新性を感じることができる作品であり、ヒップホップファンにとって必聴の一枚です。 US-ORIGINAL ーコーナーカット Media Condition Very Good Plus (VG+) Sleeve Condition Very Good (VG) Label: Sugar Hill Records – SH-32039 Format: Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM Country: US Released: 1985 Genre: Hip Hop Style: Electro Tracklist The Mega-Melle Mix DJ Mix [Mega-Mixer] – Sanny X (5:00) A1.1 Step Off A1.2 The Message A1.3 Beat Street A1.4 New York, New York A1.5 World War III A1.6 New York, New York A1.7 It's Nasty (Genius Of Love) B World War III Producer – Melle Mel Written-By – Melvin Glover, Furious Five 8:00 Credits Mastered By – CR
-

Afrika Bambaataa And The Soulsonic Force* Featuring Jungle Brothers – Return To Planet Rock (The Second Coming)
¥1,000
楽曲背景とコンセプト Afrika Bambaataaが率いるThe Soulsonic Forceは、1982年にリリースされた「Planet Rock」でヒップホップとエレクトロの融合を先駆けました。その成功から約7年後に発表された「Return To Planet Rock」は、そのコンセプトをさらに進化させ、新世代のアーティストであるJungle Brothersを迎え入れることで、1980年代から1990年代初頭への音楽的橋渡しを意図して制作されました。 • オリジナルの影響: 「Planet Rock」は、Kraftwerkの「Trans-Europe Express」や「Numbers」などのサウンドを取り入れ、ヒップホップだけでなく、エレクトロ、テクノ、ハウスの発展に多大な影響を与えました。「Return To Planet Rock」は、この歴史的遺産を継承し、アフリカ系アメリカ人音楽の文化的アイデンティティを再確認する試みです。 • 新しい要素: Jungle Brothersをフィーチャーすることで、ネイティブ・タン(Native Tongues)のクリエイティブなリリックスタイルと、Bambaataaのエレクトロフューチャリズムが融合。これは、ヒップホップの多様性を象徴するコラボレーションでした。 音楽的特徴 「Return To Planet Rock」は、オリジナルの「Planet Rock」を土台にしながら、1980年代末から1990年代初頭にかけての新しいサウンドを取り入れています。 1. プロダクション: プロデューサー陣が808ドラムマシンやサンプラーを多用し、重低音の効いたビートに未来的なシンセサウンドを加えています。 2. サンプリング: 「Planet Rock」のDNAを引き継ぎつつ、新たなサンプルを使用。特に以下の曲が注目されます: • Kraftwerk – “Tour de France” (1983年): テクノ的な要素を補完。 • Prince – “When Doves Cry” (1984年): リズムの斬新なアプローチが影響を与えています。 3. テンポとムード: • BPM: 約127 BPM、クラブでの使用を意識した高速ビート。 • ムード: エネルギッシュでフューチャリスティックなサウンドが特徴。 4. アレンジ: ラジオ向けのコンパクトなミックスから、クラブ向けのエクステンデッドバージョンまで、多様なアレンジが収録されています。 歌詞とメッセージ Jungle Brothersによるリリックは、1980年代後半におけるヒップホップの社会的・文化的なテーマを反映しています。 • テーマ: • ヒップホップカルチャーの進化 • 黒人アイデンティティの再確認 • 音楽を通じた団結と平和の訴え • 象徴的なライン: “Take a journey through time, back to where it began, the rhythm of the universe, it’s all in your hand.” このラインは、音楽の普遍性と未来への希望を象徴しています。 影響と評価 「Return To Planet Rock」は、音楽的にも文化的にも重要な作品として認識されています。 1. ヒップホップの進化: • エレクトロとヒップホップの境界をさらに押し広げ、1990年代初頭のテクノやハウスシーンへの影響を与えました。 • ネイティブ・タンとエレクトロの融合が、新しい音楽スタイルを提示。 2. クラブシーンでの成功: • 高速テンポとエレクトロニックなサウンドが、クラブの定番トラックとして人気を博しました。 3. 批評的評価: • 「オリジナルの革新性を尊重しつつ、新しい世代に訴える内容」として評価されました。 文化的意義 「Return To Planet Rock」は、Afrika Bambaataaのビジョンを未来に引き継ぎ、ヒップホップが音楽的にも文化的にも重要な存在であり続けることを証明した作品です。エレクトロとヒップホップの融合、若い世代とのコラボレーション、そして平和と団結のメッセージがこの楽曲の核となっています。 US-ORIGINAL-color vinyl Media Condition Very Good Plus (VG+) Sleeve Condition Very Good Plus (VG+) Label: York's Records – YRC-786-64-LP Format: Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Stereo, Green Country: US Released: 1989 Genre: Electronic, Hip Hop, Rock, Funk / Soul Style: Electro, Conscious, Funk, Hard Rock Tracklist A1 Return To Planet Rock (Radio Mix) 6:00 A2 Return To Planet Rock (Club Mix) 7:59 A3 Return To Planet Rock (Instrumental Mix) 5:26 B1 Inside Looking Out (Radio Mix) 4:55 B2 Inside Looking Out (Club Mix) 5:34 B3 Inside Looking Out (Instrumental Mix) 5:34 B4 Return To Planet Rock (Return Mix) 1:35 Credits Engineer – Donald Houzell Executive-Producer – Dr. York Remix – Dr. York, James Mtume Written-By – Afrika Bambaataa (tracks: A1 to A3, B4), Grand Funk Railroad (tracks: B1 to B3), Michael Small (2) (tracks: A1 to A3, B4), Nathaniel P. Hall* (tracks: A1 to A3, B4)
-

EPMD – The Big Payback
¥1,200
**「The Big Payback」**は、EPMDのクラシックヒップホップサウンドを象徴する楽曲であり、James Brownのファンクをサンプリングした重厚なビートと、直接的なリリックが魅力です。EPMDのサウンドは、後のGファンクや90年代ヒップホップにも大きな影響を与え、彼らのレガシーを確固たるものにしました。 ヒップホップ史に刻まれた「The Big Payback」は、ファンクとヒップホップの完璧な融合の一例であり、時代を超えて愛され続けるクラシックです!!!!!! 背景と制作秘話 「The Big Payback」は、EPMDが1989年にリリースした2ndアルバム『Unfinished Business』に収録された楽曲で、同年にシングルとしてもカットされました。 • EPMDの立ち位置: EPMD(Erick SermonとParrish Smith)は、80年代後半から90年代初頭にかけて、ニューヨーク・ロングアイランドを拠点に活動し、ヒップホップシーンにおけるファンクサウンドの再定義者として名を馳せました。 • アルバム『Unfinished Business』の重要性: 本作は、彼らのデビュー作『Strictly Business』の成功を受けてリリースされ、EPMDの堅実なプロダクションと洗練されたフロウがさらに進化したアルバムです。「The Big Payback」はその中でも象徴的な楽曲となりました。 楽曲タイトルの意味 • 「The Big Payback」: タイトルはJames Brownの1973年の名曲「The Payback」からインスパイアされています。復讐や報復といった意味を持つ「Payback」という言葉は、EPMDがシーンにおける存在感を示し、自らの成功を誇示する姿勢を表現しています。 リリックの内容とスタイル EPMDのリリックはシンプルでありながら力強く、ラフでありつつもクールなスタイルが特徴です。 • Erick SermonとParrish Smithの掛け合い: 「The Big Payback」では、二人のヴァースが流れるように交互に展開され、絶妙なコンビネーションが際立っています。 • テーマ: 楽曲は、自らの成功と敵に対する報復(リスペクトの奪還)をテーマにしており、シーンでの地位を揺るがせない強い自信が表現されています。 • 象徴的なライン: “You tried to front so I had to get ill…” → フロント(威張ること)した相手に対して「自分の実力を見せつける」というメッセージです。 • リリックは直接的かつ分かりやすく、当時のヒップホップファンに強烈な印象を残しました。 サウンドとサンプリング 「The Big Payback」のサウンドは、EPMDが得意とするファンクサウンドをベースにしています。 • サンプリング元: • James Brownの「Baby Here I Come」(1968年)をサンプリングし、ヘヴィなベースラインとドラムブレイクを強調しています。 • EPMDはJames Brownの楽曲を頻繁にサンプリングしており、彼らのプロダクションにおける重要な柱となっています。 • シンプルなループと重厚なビートが特徴であり、ファンクのグルーヴをヒップホップに落とし込む手法は、後のヒップホッププロデューサーたちに大きな影響を与えました。 • プロダクション: • Erick Sermonが中心となって手掛けたビートは、ミニマルでありながら中毒性が高く、ヘッドノッダー(聴いて自然に頭を振りたくなるビート)としてDJやリスナーに愛され続けています。 文化的インパクトと評価 「The Big Payback」は、EPMDのクラシックトラックの一つとしてヒップホップ史に刻まれています。 • ファンクサウンドの継承: James Brownのサンプリングを基にしたEPMDのサウンドは、Gファンクや後のウエストコースト・ヒップホップにも影響を与えました。Dr. DreやSnoop Doggらが取り入れたスタイルの先駆けとも言えます。 • 批評家の評価: 『Unfinished Business』は、リリース当時から批評家に高く評価され、**「The Big Payback」**はアルバムの中でも特に象徴的な楽曲として取り上げられました。 • The Source誌は、EPMDのプロダクションを「ファンクの再発明」と評し、彼らの音楽性の高さを絶賛しました。 • ライブでの人気: 「The Big Payback」は、EPMDのライブセットでも定番曲となり、彼らのパフォーマンスのエネルギーを象徴する楽曲となっています。 US-ORIGINAL Media Condition Very Good Plus (VG+) Sleeve Condition Very Good Plus (VG+) Label: Fresh Records – FRE-80135 Format: Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM Country: US Released: 1989 Genre: Hip Hop Tracklist X1 The Big Payback (Club Remix) 5:01 X2 The Big Payback (Instrumental Remix) 5:01 Y1 The Big Payback (LP Version) 4:15 Y2 The Big Payback (7" Remix) 3:25 Y3 The Big Payback (7" Remix Radio Edit) 3:30 Credits Design – Susan Huyser Engineer – Ivan "Doc" Rodriguez* Mastered By – Howie Weinberg Photography By – Janette Beckman Written-By, Producer, Remix – EPMD
-

Grandmaster Flash & Melle Mel - White Lines / Scorpio
¥1,200
A面: “White Lines (Don’t Don’t Do It)” 楽曲背景 • メッセージ性: 「White Lines」は、コカインや薬物使用に対する警鐘を鳴らす楽曲です。「Don’t Don’t Do It」という副題が示すように、当時のドラッグ問題を直接的に取り上げ、教育的なメッセージを発信しました。 • 社会的影響: 1980年代初頭は、アメリカでコカイン使用が拡大し、特にアフリカ系アメリカ人コミュニティに甚大な影響を及ぼしていました。この曲は、ヒップホップがエンターテインメントだけでなく、社会的な問題提起の手段としても機能しうることを示しています。 制作と音楽的特徴 • サンプリング: 楽曲のベースラインは、リッキー・リー・ジョーンズの「Double Dutch Bus」や、クラブシーンで人気のグルーヴ・ラインから影響を受けており、ファンクとヒップホップを融合させています。 • BPMと構成: 約109 BPMのミッドテンポトラックで、クラブ向けに設計されつつ、メッセージ性を保っています。 • ボーカルスタイル: Melle Melによる力強いラップと、バックコーラスの掛け合いが特徴的です。語りかけるようなフロウがリスナーに強い印象を与えます。 楽曲の成功と文化的影響 • この曲は商業的成功だけでなく、ヒップホップにおけるメッセージソングの重要性を示しました。音楽の持つ「教育」と「娯楽」という二面性を見事に融合させています。 B面: “Scorpio” 楽曲背景 • 実験的な要素: 「Scorpio」は、1980年代のエレクトロ・ヒップホップの初期を象徴する楽曲です。リズムマシンやシンセサイザーを多用し、当時としては画期的なサウンドを提供しました。 • タイトルの由来: タイトルは、グループのメンバーの一人であるスコーピオ(Eddie Morris)のニックネームから取られています。 制作と音楽的特徴 • エレクトロサウンド: ドラムマシン(特にRoland TR-808)を用いた重厚なリズムと、シンセサイザーによるメロディーラインが特徴。これにより、「Scorpio」はエレクトロ・ファンクの代表的な楽曲となりました。 • BPM: 約122 BPMのアップテンポなビートは、ブレイクダンスのシーンで非常に人気を博しました。 • ロボティックボイス: ボコーダーを使用したロボットのような声がトラックの中で繰り返され、近未来的な雰囲気を醸し出しています。 影響 • 「Scorpio」は、エレクトロとヒップホップの交差点に位置する楽曲として、多くのプロデューサーやアーティストにインスピレーションを与えました。特に、ブレイクダンスカルチャーと密接に結びついています。 文化的意義 1. 「White Lines」の意義: • 単なる楽曲を超え、ドラッグ問題に対する意識向上を目的とした社会運動的な役割を担いました。現在でもこの曲は、ヒップホップのメッセージソングの象徴とされています。 2. 「Scorpio」の意義: • エレクトロの進化において画期的な楽曲として位置づけられています。特にブレイクダンスカルチャーにおいて、音楽とダンスの相互作用を高める重要な存在でした。 3. Grandmaster Flashの影響力: • ヒップホップのパイオニアとして、単なる音楽制作だけでなく、ターンテーブリズムやサンプリング技術の進化に大きく貢献しました。 「White Lines」および「Scorpio」は、それぞれ異なる角度からヒップホップの可能性を広げた名曲です。前者は社会的メッセージを伴うパワフルなアンセム、後者は技術革新とダンスカルチャーを象徴するトラックとして、1980年代のヒップホップシーンを代表する作品となっています。 UK-ORIGINAL Media Condition Very Good Plus (VG+) Sleeve Condition Very Good Plus (VG+) Label: Sequel Records – NEET1007 Format: Vinyl, 12", 45 RPM Country: UK Released: 1999年 Genre: Electronic, Hip Hop Style: Electro Tracklist A Grandmaster Flash & Melle Mel– White Lines (Don't Do It) 7:39 B Grandmaster Flash & The Furious Five– Scorpio 4:54 Credits Lacquer Cut By – Tim D.
-

Kurtis Blow – The Breaks (Original Mix Version) (Vocal) / Rappin' Blow (Part 2)
¥1,000
The Breaks (Original Mix Version): 1. 歴史的意義 「The Breaks」は、1980年にリリースされたKurtis Blowの代表作であり、ヒップホップ史上初のゴールドディスクを獲得した楽曲です。この偉業は、ヒップホップが商業的に成功するジャンルとして認知される契機となりました。 • ヒップホップの初期成功: 「The Breaks」の成功は、Kurtis Blowがヒップホップをポップ市場に導入する架け橋的存在であったことを示しています。リリース当時、彼はMercury Recordsと契約した初のソロ・ラッパーであり、この楽曲はレーベルの信頼を得る大きな成功となりました。 • 影響: 「The Breaks」のリズム構造とコーラスのキャッチーさは、後続のヒップホップ・アーティストたちに大きな影響を与えました。この曲の「clap your hands, everybody!」のフレーズは、ライブパフォーマンスでの観客参加型スタイルの礎を築きました。 2. 音楽的特徴 • リズムとプロダクション: ファンクとディスコの要素を融合させたビートが特徴で、ギターリフやブラスセクションの使い方はJames Brownの影響を感じさせます。BPMは約113で、軽快ながらも躍動感のあるテンポです。 • 歌詞: 日常の挫折や困難をコミカルに描いた歌詞は、当時のリスナーの共感を呼びました。特に「break」という単語の多義性を巧みに利用しており、「breaks(不運)」と「break(音楽のブレイク)」を掛け合わせたリリックがユニークです。 Rappin’ Blow (Part 2): 1. 楽曲背景と位置づけ 「Rappin’ Blow (Part 2)」は、Kurtis Blowのセルフタイトル・アルバム『Kurtis Blow』(1980年)からのトラックで、デビューシングル「Christmas Rappin’」の延長線上にある楽曲です。パート2として発表されたこの曲は、彼のストーリーテリング能力とフロウのスムーズさを強調しています。 • リリース背景: 「Rappin’ Blow」は、パーティートラックとしての要素が強く、ディスコやクラブでのプレイを想定して作られました。BPMは約110で、ダンサーにとって程よいテンポです。 • アーティストとしての成長: この楽曲では、Kurtis Blowが「The Breaks」よりもさらに柔軟なフロウとライミング技術を披露しており、彼のアーティストとしての進化が見て取れます。 2. 音楽的特徴 • ベースラインとリズム: 「Rappin’ Blow」は、よりファンク色が強く、太いベースラインが楽曲を支えています。ディスコビートを土台にしたプロダクションが、当時のトレンドと一致しています。 • ヴォーカルスタイル: Kurtis Blowの独特の落ち着いた声色と、リズムに乗ったナレーションスタイルのラップが際立っています。 文化的影響 1. ヒップホップ史への貢献 Kurtis Blowは、「The Breaks」を通じてヒップホップを世界的な現象に押し上げる役割を果たしました。その音楽性や商業的成功は、Run-D.M.C.やLL Cool J、さらにはPublic Enemyなど、次世代アーティストたちに多大な影響を与えています。 2. ヒップホップのルーツの保存 「Rappin’ Blow (Part 2)」のような楽曲は、ヒップホップがどのように進化し、どのような影響を受けたのかを知る手がかりとなります。これらのトラックは、ジャンルのルーツを振り返るうえで欠かせないものです。 Germany盤 Media Condition Very Good Plus (VG+) Sleeve Condition Very Good (VG) Label: ZYX Records – ZYX 5595, ZYX Records – 5595 Series: The Golden Dance-Floor Hits – Vol. 7 Format: Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single, Repress Country: Germany Released: 1987年 Genre: Hip Hop, Funk / Soul Style: Disco Tracklist A The Breaks Written-By – J.B. Moore, K. Blow*, L. Smith*, R. Ford*, R. Simmons* 7:41 B Rappin' Blow (Part 2) Written-By – D. Miller*, J.B. Moore, K. Blow*, L. Smith*, R. Ford* 4:41 Credits Lacquer Cut By – SST (8) Producer – J.B. Moore, R. Ford, jr.
-

Doowutchyalike - Digital Underground
¥1,800
ファンキーなヒップホップのパーティーアンセム!!!!!! サンプリング元としても!!! Digital Undergroundの「Doowutchyalike」は、1989年にリリースされたファンキーなヒップホップのパーティーアンセムで、彼らのデビューアルバム『Sex Packets』からのシングルです。この曲はShock G(フロントマン)がプロデュースし、Tommy Boy Recordsからリリースされました。この楽曲の特徴は、自由で楽しむことをテーマにしたリリックと、シンプルながらもキャッチーなリズムセクションです。 「Doowutchyalike」は、ファンキーなビートとユニークなアプローチでヒップホップにエンターテイメント性をもたらし、ユーモアあふれるリリックと独創的なスタイルで注目を集めました。収録バージョンには8分54秒の「Playhowyalike Mix」や、4分48秒のラジオミックスもあり、当時のクラブシーンで非常に人気がありました。レコードはアメリカ以外にもイギリスやドイツ、フランスでも流通し、コレクターの間で評価されています。 この曲は後に他の多くのヒップホップトラックにサンプリングされ、ジャンルにおけるパーティーサウンドのクラシックとされています。また、映画『Love & Basketball』にも使用され、さらにその知名度を上げました。 US-ORIGINAL Media Condition Near Mint (NM or M-) Sleeve Condition Near Mint (NM or M-) Label: Tommy Boy – TB 932, TNT Records (2) – TB 932 Format: Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM Country: US Released: 1989年 Genre: Hip Hop Style: P.Funk Tracklist A1 Doowutchyalike (Playhowyalike Mix) Written-By – G. Jacobs* 8:54 A2 Hip Hop Doll (Vocal Mix) Written-By – G. Jacobs*, K. Waters* 5:30 A3 Doowutchyalike (Instrumental Mix) Written-By – G. Jacobs* 4:58 B1 Doowutchyalike (Radio Mix) Written-By – G. Jacobs* 4:48 B2 Hip Hop Doll (Instrumental Mix) Written-By – G. Jacobs*, K. Waters* 5:33 B3 Doowutchyalike (Underground Like-Appella Mix) Written-By – G. Jacobs* 4:25 Credits Arranged By [Turntable Arrangements By] – Kenny K Concept By [Addition To The "Doowutchyalike" Concept By] – Earl Cool*, Kent Racker Executive-Producer – Atron Gregory Illustration – Rackadelic Mixed By [All Selections] – The Underground-Mixhowyalike Posse* Mixed By [Pushin' The Knobs] – Richie Corsello*, Steve Counter Producer – Shock G Producer [Preproduction By] – Kevin Jones (2) Turntables [Turntables Performed By] – DJ Goldfingers*